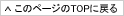2013年度
第33回全国大会 プログラム
| 日時 | 2013年11月10日(日)10:00~17:45 |
|---|---|
| 場所 | 成蹊大学 3号館 101教室 〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
| 交通 | JR中央線・総武線(東京メトロ東西線)・京王井の頭線 吉祥寺駅 下車 吉祥寺駅北口バスのりば1・2番より関東バス 成蹊学園前下車 約5分 吉祥寺駅より 徒歩約15分 |
| 受 付 (9:30~10:00) | ||
| 開会の辞 (10:00) | ||
| 成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 | |
| Ⅰ 研究発表(10:00~11:00) | ||
司会 |
上智大学准教授 | 松 本 朗 |
| 『波』におけるロマンスの構造とクレオール的主体 ―「もし、僕(ルイス)がカナダ人かオーストラリア人だとしたら、僕は異国人でよそものなのだ」― |
||
| 東北学院大学非常勤講師 | 漆 原 幸 子 | |
司会 |
東洋英和女学院大学教授 | 奥 山 礼 子 |
| ‘Beautifully Looked After’――マンスフィールド「蝿」と戦没者墓地の美化の問題 | ||
| 東北学院大学大学院生 | 畠 山 研 | |
| Ⅱ ワーク・イン・プログレス報告(11:00~12:00) | ||
司会 |
青山学院大学准教授 | 麻 生 え り か |
| 断片を越えて――第三波フェミニズムからみる戦間期女性文学 V・ウルフ『歳月』に探る女の連帯の(不)可能性 |
||
| 日本女子大学非常勤講師 | 丹 羽 敦 子 | |
| 英国大戦間期の女子の職業選択と主体構築 | ||
| 帝京大学講師 | 松 永 典 子 | |
| Ⅲ 総 会(13:20~13:40) | ||
司会 |
九州大学教授 | 鵜 飼 信 光 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 東京家政大学教授 | 伊 藤 節 | |
| Ⅳ シンポジウム(13:40~16:20) | ||
| ウルフと教育 | ||
司会・講師 |
一橋大学准教授 | 河 野 真 太 郎 |
講師 |
東洋大学教授 | 矢 口 悦 子 |
講師 |
東洋大学講師 | 井 上 美 雪 |
講師 |
埼玉大学准教授 | 武 田 ち あ き |
| Ⅴ 特別招待発表(16:30~17:30) | ||
司会 |
成蹊大学教授 | 遠 藤 不 比 人 |
| Exorcising the Figure: Virginia Woolf's and Vanessa Bell's Faceless Subjects | ||
| 成蹊大学客員研究員 | Dr. Kamilla Pawlikowska | |
| 閉会の辞 (17:30) | ||
会長 |
東京家政大学教授 | 伊 藤 節 |
| 懇 親 会 (17:45~19:45) | ||
会場ワインビストロカフェ「ゴブラン」 |
||
| 会費5000円(学生 3500円) | ||
研究発表要旨
『波』におけるロマンスの構造とクレオール的主体
―「もし、僕(ルイス)がカナダ人かオーストラリア人だとしたら、僕は異国人でよそものなのだ」―
東北学院大学非常勤講師 漆原 幸子
『波』(1931)の中心人物パーシヴァルの名称や人物造形は、フランス中世のロマンス「ペルスヴァルの物語」を髣髴させ、その「非英雄性」(遠征先で落馬して死ぬ)や「野蛮性」(突然見知らぬ女性にキスをする)を想起させるが、興味深いのは、それが「ジニーがルイスにキスをする」という挿話を巡って、視点人物の一人ルイスに転移され、更には、同時代のインターテクストを通して、過激な形で反復され、前景化されていることである。本発表では、こうした要素が「被植民者」としてのルイスの「野蛮性」や「異質性」を表すだけではなく、パーシヴァルの死後、「太平洋」を渡ってグローバルな経済支配を展開して行くルイスの「植民者」としての「パラノイア」としても表象されていることに着目しながら、ルイスの主体構築を考察する。結論として、パックス・ブリタニカに代わるパックス・アメリカーナの価値観が称揚されるのではなく、その中で再編しうる「英国性」への疑義が、被植民地出身のルイスの視点を通して示されていることを提示してみたい。
‘Beautifully Looked After’――マンスフィールド「蝿」と戦没者墓地の美化の問題
東北学院大学大学院生 畠山 研
キャサリン・マンスフィールド(Katherine Mansfield, 1888-1923)の「蝿」(‘The Fly,’1922)は、第一次大戦後、ある初老の男が息子の戦死の記憶に苦悩する様子を描く物語である。本発表では、先行研究でまだ十分議論されていない点として、戦没者墓地の問題を取り上げたい。物語のなかで、墓地は自然の美しさを備えていることが言及されるが、そのような美化は戦争の悲惨さを覆い隠す側面がある一方、多くの男たちを同一の場所で埋葬する際に個々の兵士たちの区別を無にするものでもあった。これらの点を踏まえ、蝿の死の場面を読むとき、本発表では、大戦の戦場に関わる重要な問題が垣間見えることを論じる。
ワーク・イン・プログレス報告要旨
断片を越えて――第三波フェミニズムからみる戦間期女性文学
V・ウルフ『歳月』に探る女の連帯の(不)可能性
日本女子大学非常勤講師 丹羽 敦子
ネオリベラリズム的個人主義の影響下で生まれたポストフェミニズムに応答する形で登場したと、第三波フェミニズムを位置づける場合、それは女の連帯の必要性を説くものだとしばしば指摘される。だがその連帯とはどのようなものなのか。「連帯」といえば、政治的改革を求めた第二波フェミニズムの場合を想起させるが、それとはどのように違うのか。そもそも何をもって女たちはつながり得るのか。本発表では、「連帯」をめぐるこうした疑問を考えるためのヒントを、ウルフの『歳月』のなかに探ってみたい。なぜなら『歳月』では、世代を超えおそらく階級をも超えた女同士のつながりを試行した末に、それに失敗していると思われるからである。ウルフが模索し達成しえなかった女の連帯とはいかなるものなのか。第三波フェミニズムが示唆するとされる「連帯」の必要性を『歳月』を通して考察し、作品のなかに女同士の新たなつながり方の可能性を探りたい。
英国大戦間期の女子の職業選択と主体構築
帝京大学講師 松永 典子
女の労働はフェミニズムにおいて重要な課題である。しかし、経済的自立を得ようとしたウルフの同時代の女たちと、個人主義的な「女性の社会進出」を称揚する現代の女たちとで、その課題は同じなのだろうか。言い換えるなら20世紀初頭の女性参政権という社会運動を担ったフェミニストたちと、個人の努力によってこそ自己実現が可能とされる今日のポストフェミニズム的状況における女たちとに共有すべき問題はあるのだろうか。こうした問題意識のもとに、本発表では、女・労働・自由をキーワードに、20世紀初頭における女子の職業選択に注目し、とくに大戦を舞台にした小説(Irene Rathbone,We That Were Young(1936)等)に描かれた二種類の看護婦(職業看護婦とボランティア看護婦)の女性表象を取り上げ、職業選択する女たちのおかれた状況と職業人としての彼女たちの仲間意識を断片化する言説を考察する。まず第一次大戦開始以前および戦間期の女子の職業選択とその意識を確認し、次に上記二種類の看護婦の職業意識を分析し、彼女たちが何を求め、どのようなアイデンティティ形成をおこなったかを明らかにする。以上のような発表をとおして、階級によって分断されず、市場原理に限定されることのない、女の連帯すなわちフェミニズムの可能性を探りたい。
第33回日本ヴァージニア・ウルフ協会大会シンポジウム要旨
ウルフと教育
| 司会・講師 | 一橋大学准教授 | 河野 真太郎 |
| 講師 | 東洋大学教授 | 矢口 悦子 |
| 講師 | 東洋大学講師 | 井上 美雪 |
| 講師 | 埼玉大学准教授 | 武田 ちあき |
ヴァージニア・ウルフが、作家となる前に成人教育に携わっていたこと、またエッセイ『私一人の部屋』や『三ギニー』が女性の教育を重要な主題としていることは周知の通りである。「ウルフと教育」をテーマとする本シンポジウムは、そういった事実を踏まえつつ、教育というものは広く社会の変化を反映しつつ、同時に社会に変化をもたらすものだ、という認識に基づいて、ウルフと、同時代の文学や文化・社会における教育や人間の成長の観念について考察する。
その社会の変化を表すもっとも広い言葉は、「リベラリズム」であろう。ウルフの生きた19世紀終わりから20世紀中葉にかけてのイギリスの教育の制度と文化は、リベラリズムに基づく教育機会の拡大によって特徴づけられる。ウルフ自身は、むしろその変化の恩恵を受けない階級(「教育ある男性の娘たち」)に属したのだが、それにしてもウルフ自身と、そのリベラリズムのイデオロギーとの深い関係は、近年国内外で注目され研究が進んでいるところである。
またウルフの時代の教育が注目されるのは、その時代の変化が私たちの生きる現在の系譜をなしているためでもある。ここで念頭にあるのは、ウルフの死後にイギリスで成立する福祉国家とその下での教育、そしてその後の新自由主義「革命」以降の教育であり、そういった変化を支える制度のみならず感情のあり方が、ウルフの時代に醸成されていたのではないか。これもまた、「リベラリズムの変容」という表現に包含しうる主題であろう。
より具体的には本シンポジウムでは、イギリスにおける教育制度の変容(一般的な公教育だけでなく成人教育も含めたそれ)を検討するのと同時に、教育をめぐる「経験」を文学作品の中に求め、その両者を統合しつつ広い時代像をつかむことを目的とする。
ウルフと(成人)教育?
一橋大学准教授 河野 真太郎
河野は司会として、「ウルフと教育」というテーマを設定した際の基本的な問題のありかを指摘したい。例えばウルフは1905年からモーリー・コレッジで労働者階級の女性を対象とする歴史の講義を行っていた。どうやらうまくはいかなかったこの講義の、ウルフにとっての意味は、そしてウルフの作品との関係は何か。また、教育を直接の話題とするテクストは『私ひとりの部屋』と『三ギニー』(さらには「斜塔」など)であるが、これらを改めて教育論として読んだらどのように読めるのか、またウルフに対するQ. D. リーヴィスの批判が物語ることは何か。さらに広くは、教育にまつわるウルフの階級的限界(教育という主題に関して、ウルフの階級は「残滓化」しつつあったこと)を理解した上で、それでもなおウルフに積極的な可能性を見いだすことは可能か。言い方を変えれば、レイモンド・ウィリアムズの言う「長い革命」(教育の変化はその重要な因子)の一部に、ウルフを位置づけるかとは可能なのか不可能なのか。できる限りの論点提示をしたい。
成人教育における「偉大な伝統:リベラリズム」の確立と女性たちの学習
東洋大学教授 矢口 悦子
19世紀末から1920年代半ばまでの時期は、英国成人教育の歴史において顕著な特徴を持つ。この時期順次成立した教育関連法は、労働者階級の人々への初等教育機会と職業技術教育の整備をもたらしたが、そうした動きに対して、敢えて労働者に大学レベルの高等教育を提供することを求めた労働者教育協会(WEA)が1903年に成立する。WEAは階級闘争や革命の手段としての教育ではなく、労働者の精神的な解放と社会的な解放を希求する運動として成人教育を展開した。その背景には、労働者の急進的な運動への傾斜を防ぎ、穏健な形で協調的な路線に取り込みたいと考えていた国教会系の重鎮である大学関係者の援助があったことは広く知られている。ここで提起された「非職業的一般教養教育を労働者へ」という理念は「成人教育におけるリベラリズム」としてこののち長く引き継がれる。その理念は、イギリス成人教育の画期とされる「1919年報告書」の基本理念と重なり、主としてWEAと大学とが地域における成人教育提供の責任を持つ団体として認定された1924年の成人教育規則の成立を促した。
本報告では、このように成人教育が制度として整えられる時期にあって、具体的な人々の学習の実態はいかなるものであったのか、特に、女性たちはこのイデオロギーのもとでどのような学習活動を展開していたのかという視点から検討を試みる。時は、女性たちによる協同組合運動の発展、婦人参政権運動、女性高等教育機関の拡大というように、様々な女性運動が同時に繰り広げられていた時期である。成人教育の現場に注目することで、「労働者」、「主婦」、「未婚・既婚」などという区別がもたらしていた女性たちの分断とそのユニークな共存関係に迫ることができればと考えている。
To the Lighthouseにおける教育と福祉
東洋大学講師 井上 美雪
To the Lighthouseにおいて、貧困、失業、身体虚弱といった社会問題を解決すべく関心を寄せているのが、Mrs. RamsayとCharles Tansleyである。前者は当時のチャリティ団体が実施していた戸別訪問による実地調査を通じての健康状態改善を目指し、後者はセツルメントや講義や講演を通して問題の解決を訴えるのである。同じ問題に対し慈善・福祉と教育からアプローチしているが、両者はともに自助の精神を賞揚している。だが第1部が設定されている1900年代後半では、レッセ・フェールの時代からニュー・リベラリズムの時代へとイギリス社会は変遷を遂げているただなかであり、教育・福祉政策ではセルフ・ヘルプ的個人主義は後退していっていたのであった。本発表では本作品において教育・福祉とそれを支える価値観がいかに変遷しているかを確認したうえで、ウルフの階級意識に縛られた教育観を明らかにしたい。
帝国教育の堕天使たち ――落第生の系譜と戦間期の学校小説
埼玉大学准教授 武田 ちあき
19世紀以降の英国小説に脈打つ隠れた伝統に「落第生の系譜」がある。かれら大英帝国の落ちこぼれが実は広く国民に愛され続けており、その黄金時代がモダニズムと重なっていることは興味深い。こうした落伍者たちが特に1920年代、いわばもてはやされた背景にはイギリスの学校制度へのアンビヴァレントな国民感情があり、ノスタルジー/ファンタジーとして英国性が温存される作品空間には、それを許さない戦間期の社会不安の亀裂が走っていた。ミルン、ウッドハウス、ウォー、ヒルトン、コンラッドらの描き出す落第者たちの世界を概観し、落第生という視座が逆照射するイギリス教育制度の姿を検討する。
特別招待発表要旨
Exorcising the Figure: Virginia Woolf's and Vanessa Bell's Faceless Subjects
Kamilla Pawlikowska
Seikei University
British Academy/Japan Society for the Promotion of Science Postdoctoral Research Fellow
Radically reconfiguring the image of the human face, modernist portraits have been often vigorously debated. However, Virginia Woolf's and Vanessa Bell’s contributions to the revolution in modernist portraiture have not received sufficient critical attention. This presentation focuses on Woolf's and Bell's creative experimentation with faces and their implications in the process of subject-formation.
Bell's portraits of Woolf from 1912 depict the sitter with a blank face whose idiom escapes conventional physiognomic interpretations. Woolf herself emphasises, that in Bell’s portraits ‘No stories are told; no insinuations are made’ since they do not rely on language or words. In her writing, Woolf not only avoids physiognomic descriptions but also celebrates the withdrawal of the face; her short story ‘The Lady in the Looking Glass: A Reflection’ (1929) is a notable example of this. Both artists obstruct the possibility of a physiognomic reading of the face in order to (as Woolf suggests) render it resistant to death. Would this imply that the face is death itself? Indeed, Deleuze and Guattari argue that the visibility of the figure/face (the French word figure means both) triggers the person's symbolic death. Once we have seen somebody's face and established its ‘meaning’, we spontaneously form stereotypical judgements which help us to construct the person as the ‘subject’. Hence, the face does not index some hidden ‘depth’, but activates a set of pre-determined automatic responses. This presentation will examine how Woolf's and Bell’s aphysiognomic strategies of writing and painting the face deactivate procedures of signification and subjectification in order to re-establish the possibility for an authentic communication.