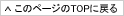2023年度
第43回全国大会 プログラム
| 日時 | 2023年11月4日(土) 10:20〜17:40 |
|---|---|
| 場所 | 東京大学駒場キャンパス18号館1階ホール 〒153-8902 東京都目黒区駒場3丁目8−1 |
| 開催形態 | ハイブリッド |
| 受付(9:50〜) | ||
| 開会の辞 (10:20) | ||
| 青山学院大学教授 | 麻 生 え り か | |
| 開催校挨拶(10:25) | ||
| 東京大学教授 | 田 尻 芳 樹 | |
| Ⅰ 研 究 発 表(10:30~12:00) | ||
|
司会
|
大東文化大学准教授 | 菊 池 か お り |
| 『ダロウェイ夫人』における植物たちとの危うい生──トラウマ、優生学、偶然性 | ||
| 東京大学大学院生 | 西 脇 智 也 | |
|
司会
|
福岡大学准教授 | 岩 崎 雅 之 |
| 「彼女ひとりの部屋」はあるのか──『灯台へ』における「家」とラムジー夫人の自己 | ||
| 神戸女学院大学非常勤講師 | 佐 藤 エ リ | |
| Ⅱ 総会(12:05〜12:35) | ||
|
司会
|
早稲田大学准教授 | 松 永 典 子 |
| 会計報告、編集委員会報告、次期大会、その他 | ||
| 九州大学教授 | 鵜 飼 信 光 | |
| 昼食は会場外でお願いします。ご持参の昼食は18号館4階のオープンスペースにておとりください | ||
| Ⅲ シンポジウム(13:45〜16:15) | ||
| ウルフ、マンスフィールド、そしてアリ・スミス──英語圏女性作家の影響/継承 | ||
|
司会
|
相愛大学教授 | 石 川 玲 子 |
|
講師
|
大分大学講師 | 大 谷 英 理 果 |
|
講師
|
秋田大学講師 | 畠 山 研 |
|
講師
|
東京理科大学講師 | 西 野 方 子 |
| Ⅳ 特別講演(16:30〜17:30) | ||
|
司会
|
青山学院大学教授 | 麻 生 え り か |
| ヴァージニア・ウルフが見た「日本」──作家の船出を考える | ||
| 都留文科大学名誉教授 | 窪 田 憲 子 | |
| 閉会の辞(17:35) | ||
|
会長
|
九州大学教授 | 鵜 飼 信 光 |
| 懇親会(18:00〜20:00) | ||
| 会場:生協駒場食堂(駒場キャンパス内)3階 会費:6000 円(学生 3000 円) |
||
研究発表・シンポジウム・特別講演 要旨
研究発表 要旨
『ダロウェイ夫人』における植物たちとの危うい生──トラウマ、優生学、偶然性
東京大学大学院生 西脇 智也
本研究報告は『ダロウェイ夫人』における植物の表象を生存の問題という観点から考察する。本作における植物は、作中のロンドンおよび過去のブアトンの時空間に様々な形で存在するありふれた日常的なものであると同時に、シルヴィアの死を招いてクラリッサの無神論的な考えの遠因となった倒木、樹木の生命感に高揚させられるセプティマスなど、病気や戦争などでトラウマを抱えた登場人物たちの死生観という本作の重要な主題とも結びついている。とりわけ、自分の死後にも植物などに形を変えて自分の何かが残ると考えるクラリッサの意識を通じて、人間と植物という種の固定性を問いに付す生存の問題が導入されている。この哲学的視点を、セプティマスに「人間性」の悪しき象徴と見なされるサー・ウィリアム、およびブルートン夫人らが体現する優生学的思考と比較することで、その政治性についても考察したい。これらの人物は、上流階級の移民および精神失調者の隔離と生殖の禁止という生政治的な手段により、血統に基づく帝国主義的秩序の過去から未来への継続を確保しようと考える。未来に生き延びるべき人間を排他的に定義するこうした優生学的思考に対して、クラリッサとセプティマスの植物との関係や、人気なき草原と化した遥か未来のロンドンを描く語りなどを通じて、未来における人間の存在を絶対視しない非人間中心的な時間性が導入されるのである。
「彼女ひとりの部屋」はあるのか──『灯台へ』における「家」とラムジー夫人の自己
神戸女学院大学非常勤講師 佐藤 エリ
中産階級を中心としたヴィクトリア朝の性別役割分業により、女性たちは「家庭の天使」として、私的領域である家庭に閉じ込められた。一方、その領域内で妻そして母としての役割を果たし、家事を切り盛りする彼女たちは、閉じ込められた存在でありながら、家庭内で「女主人」となる、という逆説も生まれた。『灯台へ』(To the Lighthouse, 1927)において、ラムジー夫人はまさに、この逆説を体現する人物であると同時に、「家」自体が彼女を象徴するものとして描かれてもいる。
しかし「家」の持つ役割は、二元的な価値観において、単なる女性の場としての私的領域と規定されるものではない。「家」は、その内部に配置された台所、居間、食堂、寝室、子供部屋、書斎といった他者にも占有された多様な空間を内包した場である。そしてそれぞれの場所で、女性の役割や他者との関係性における女性の立場も流動的に変化する。
本発表では、自己と他者との境界が曖昧となる「家」において、ラムジー夫人の自己が、どのように描かれているかに着目する。「家」の空間の持つ多様性から、本来は自己の外部であるはずの他者が、ラムジー夫人の自己形成にどのように関わっているかを検証することにより、ヴィクトリア朝の家庭の天使像を超えた彼女の複雑さを明らかにする。考察にあたっては、彼女に対する他者──とりわけラムジー氏やリリー──の視点にも注目する。
シンポジウム要旨
ウルフ、マンスフィールド、そしてアリ・スミス──英語圏女性作家の影響/継承
| 司会 | 相愛大学教授 | 石川 玲子 |
| 講師 | 大分大学講師 | 大谷 英理果 |
| 講師 | 秋田大学講師 | 畠山 研 |
| 講師 | 東京理科大学講師 | 西野 方子 |
同世代の女性作家として交流があり、互いに複雑な感情を抱き合っていたウルフとマンスフィールドを並べた研究は、すでに多くなされている。これからも両者について新しい切り口からの研究が期待されるが、マンスフィールド没後から 100 年の節目にあって、本シンポジウムではウルフとマンスフィールド、そして現役の女性作家アリ・スミスを並べ、3 人の作家に共通して見られる「越境」というテーマを念頭に置きつつ、時空を越えた作家同士の直接・間接の影響/継承関係を考察する。
シンポジウムの前半では、ウルフとマンスフィールドの作品をいくつかの文化的項目──「慈善」「戦争」「パーティー」「旅」──に焦点を当てて論じ、今現在を生きる私たちが 20 世紀前半に書かれたウルフとマンスフィールドの作品を読むことの意義を示す。その議論を踏まえた上で、シンポジウムの後半では、この 2 人の作家について鋭く機知に富んだコメントを複数の場で発信している現代の作家アリ・スミスの作品を取り上げ、3 作家の作品にどのような繋がりが見られるのかを検討する。ウルフとマンスフィールドの作品に男女間の不平等や階級格差が描かれているように、アリ・スミスのテキストにもまた、ブレグジット前後以降さまざまな分断や格差、不寛容の顕在化した現在のイギリス社会が描き出されている。3 人の作品でこれらの諸問題がどのように扱われ、分断された領域を越えることについて何が語られているのか比較しながら辿ることで、ウルフ、マンスフィールド、そしてアリ・スミスの新しい研究の可能性を模索する。また、それによりウルフとマンスフィールドの現代性を浮き彫りにすることをも目指したい。(石川玲子)
旅からパーティーへ──マンスフィールドとウルフの象徴的なつながり
大谷 英理果
本発表ではマンスフィールドの「園遊会」(“The Garden Party”)とウルフの『ダロウェイ夫人』 (Mrs. Dalloway)を主に取り上げる。両作品は、パーティーが開催される 1 日を描き、そのパーティーに死が入り込むという共通の設定を共有しているが、パーティーの女主人を務める主人公の年代は、それぞれ思春期と中年期という違いを伴う。本発表では、両作品の比較に関する先行研究に言及しながら、「園遊会」と『ダロウェイ夫人』に描かれる(非)日常性を象徴するパーティーの役割と両作品に共通する物語の非完結性に関して考察を行いたい。その中で、マンスフィードとウルフの交流が始まる前に書かれた 2 人の初期作品に描かれる旅表象にも着目し、旅とパーティーという新たな観点から、両作家の作品を分析することで、モダニスト女性作家としての 2 人の象徴的なつながりを再検討したい。
Charity & Money──家庭の天使の「継承」から読むマンスフィールドとウルフ
畠山 研
本発表ではマンスフィールド「人形の家」(“The Doll’s House”)とウルフ『灯台へ』(To the Lighthouse)を取り上げる。「人形の家」では家庭の天使的な女性が不在で、慈善的行為を欠く女性たちの冷たい態度が子供たちに「継承」される懸念がある。『灯台へ』ではラムゼイ夫人が家庭の天使のように描かれ、慈善活動に熱心だが、死後、その信念が次世代に「継承」されるのか、議論を要する。荒れた別邸に管理費が支払われるだけであることを不満に思う労働者階級のマクナブ夫人が、もしそのお金でバスト夫人やその息子を仕事仲間に迎えていたとしたら、大戦の不況を背景に労働者の救済がある一方、人と人のつながりの希薄化、労働する個人の矮小化も発生し、またそれらと対抗するようにクローズアップされる労働者たちの内面も再注目され、さまざまな問題が交差するさまを読むことができるのではないか。
境界を越える視覚表現──アリ・スミス『春』に見られるウルフとマンスフィールドの痕跡
西野 方子
本発表では、ウルフとマンスフィールドが現代の作家にどのように継承されているかを示す一例として、スコットランド出身の現代作家アリ・スミスを取り上げる。ポスト・ブレグジット小説として知られるスミスの四季 4 部作の 3 作目『春』(Spring)では、マンスフィールドが過去の実在の作家として、また同時に架空の物語(映像化予定の小説)の主人公として登場する。その作品の映像化をめぐり展開される現実と虚構、写実と物語、見えるものと見えないものについての問いは、作品の主題である越境という行為に関して様々な可能性を提示する。本発表では、マンスフィールドの「ピクチャーズ」(“Pictures”)やウルフの「壁のしみ」(“The Mark on the Wall”)など映像や視覚に関連する作品を参照しながら、『春』における映像表現・視覚表現をめぐる議論から浮かび上がる越境のあり方を論じ、スミスの作品におけるウルフとマンスフィールドの痕跡を辿る。
特別講演 要旨
ヴァージニア・ウルフが見た「日本」──作家の船出を考える
窪田 憲子
ヴァージニア・ウルフが日本に関心をもった作家であった、ということは一般にはあまり知られていないであろう。むしろ、Nigel Nicolson が言うように、ウルフは xenophobia だったという見方の方がよく知られている。しかし、ウルフの作家活動を見ていくと、とくに初期においては日本との関連が強く出されている。今回は、そのようなウルフの日本に対する関心が具体的にはどのようなものであったのか、なぜあまり知られていないのか、また 19 世紀後半から20 世紀前半のイギリスにおける「日本」の存在を構成していた諸々の文化現象にどのような特徴があったのか、ということについて見ていきたい。そして、初期のウルフの「日本」に対する関心が、その後のウルフの文学にどのような存在としてあり続けたのか、ということを考察してみたい。とりあげる作品は、主として Charlotte Lorrimer, The Call of the East (1907) とウルフのその書評、そしてウルフの初期の作品 ‘Friendships Gallery’ (1907) および Moments of Being (1976) を考えている。