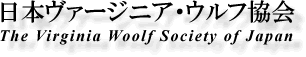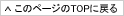3月例会のご案内
2025年3月例会を、下記の要領で3月9日(日)に開催いたします。
第130回例会(2025年3月例会)
- 日時
- 2025年3月9日(日)
14:00~16:25 - 会場
- 神戸大学六甲台第2 キャンパス 人文学研究科B 棟B135 教室
- 交通アクセス
- https://www.kobe-u.ac.jp/ja/campus-life/general/access/rokko/
- バス
- JR「六甲道」駅、阪急「六甲」駅より神戸市バス36系統(鶴甲団地域・鶴甲2丁目止まり行き)乗車、「神大文理農学部前」下車(それぞれ15分、10分。タクシーの場 合はそれぞれ10分、5分程度。)
- キャンパス
マップ - https://www.kobe-u.ac.jp/ja/campus-life/general/access/rokko/rokkodai2/
| 研究発表 | ||
| 1.松崎翔斗(呉高等工業専門学校)14:00~15:00 | ||
| 「ウルフとエピファニー―レイモンド・ウィリアムズの「ブルームズベリー分派」の視点から」 “Woolf and Epiphany: From the Perspective of ‘The Bloomsbury Fraction’ by Raymond Williams” |
||
| 2.四戸慶介(岐阜聖徳学園大学)15:15~16:15 | ||
| 「『歳月』と『失われた地平線』にみる異なる文明としてのチベット」 “Tibet as Another Kind of Civilisation in The Years and Lost Horizon” |
||
3月例会の発表概要
研究発表1
ウルフとエピファニー―レイモンド・ウィリアムズの「ブルームズベリー分派」の視点から
呉高等工業専門学校
松崎翔斗
ヴァージニア・ウルフ (Virginia Woolf [1882-1941]) の小説やエッセイにおいて、登場人物やウルフ自身が啓示あるいはエピファニーを得る瞬間が記述されることがある。たとえば、『灯台へ』(To the Lighthouse [1927])において、ラムジー夫人 (Mrs. Ramsay) は灯台の光を見つめているとき、神の御手にあると不意に言ってしまう。ウルフがいう「存在の瞬間」(‘moments of being’) もまた、エピファニー的なものである。セント・アイヴス (St Ives) の庭で花壇を見ていたとき、花が大地の一部であると突如として悟ったことが、具体例のひとつとして挙げられる。以上のような例に加えて、なかには、啓示を受ける瞬間に歩いていることもある。しかし、歩くこととエピファニーの獲得との関連についてはあまり触れられてきていないように思える。したがって、本発表では、歩くという行為が、ウルフの著作におけるエピファニー獲得において、どのような働きをしており、どのような意義を持っているのかを考察してみたい。「歩く」というのは、当然、移動のメタファーとして読むことができるため、本発表では特に、その暗示的な意味を「階級間移動」に見出して考察してみたい。ウルフとエピファニーの獲得を考えるとき、精神の自由が関わっていることは明らかである。彼女が身を置いていたヴィクトリア朝的な家庭環境に、ウルフが精神の自由を求めるに至る理由を見出すことができるであろうし、それを登場人物に反映するのも頷けるだろう。精神の自由あるいは自由な空気というものは、ちょうどウルフが所属していた、ブルームズベリー・グループ (Bloomsbury Group) のそれと類似している。レイモンド・ウィリアムズ (Raymond Williams [1921-1988]) は「ブルームズベリー分派」(‘Bloomsbury Fraction’ [1978]) において、ブルームズベリー・グループの特色や特質が、個々の信条が自由であることと、上流階級的なものであることを指摘している。このことを踏まえれば、ウルフが求める自由とは、上流階級の空気であったということができるだろう。そのような精神的自由は、ウルフの小説やエッセイにおいて、エピファニー獲得の兆しとして描かれることがある。加えて着目したいのは、啓示を受ける者が歩いているときがあることである。具体例として、『船出』(The Voyage Out [1915]) において、レイチェル・ヴィンレイス (Rachel Vinrace) は、歩いている最中に、精神の自由を得るや否や、突如として世の真理を見出す場面がある。
以上のように、ウルフの小説やエッセイにおいて、歩くという行為を介してエピファニーが得られる瞬間があることを考慮に入れると、「歩く行為」は上流階級への移動のメタファーとして読むことができるだろう。本発表では、ウィリアムズの「ブルームズベリー分派」を手掛かりに、エピファニーの獲得と歩く行為との関連を、ウルフの小説とエッセイに見出したい。しかし、ウルフにおけるエピファニーを考えるとき、彼女自身が患っていた精神疾患に目を配ることも忘れてはならないだろう。したがって、「歩く行為」が「階級間移動」のみならず、ウルフの「精神状態の移行」―鬱状態から躁状態への移行―のメタファーでもあることを最後に指摘し、本発表を終えたい。
研究発表2
『歳月』と『失われた地平線』にみる異なる文明としてのチベット
岐阜聖徳学園大学
四戸慶介
2024年11 月に行われた日本ヴァージニア・ウルフ協会第44 回全国大会の研究発表「「ビルマにいましたのよ」——ウルフと水島のあいだに、あるいは、日英文学のユーラシア表象の可能性」(髙田英和)において、ウルフの自死に至る行為を再考するにあたって、20世紀の文学が展開を求めて舞台に選んだユーラシア大陸の南東/東南地域の重要性について言及がされた。『ダロウェイ夫人』のピーター・ウォルシュとヒマラヤ、ビルマの関係といった微細な設定は、「イギリスの」文学が植民地を舞台に形成されていく過程や、レナードをはじめとするウルフ周辺の人々が彼女とユーラシア地域とを媒介することを考慮すれば、不可欠な設定である。ウルフは1937年の『歳月』においても、例えばチベットについて、非常に小さくではあるが印象的な言及をしている。そこで本発表では、そのような微細なチベットへの言及が、『歳月』が出版される頃のイギリスにとってどのような意味を持ち得るのか、『歳月』とは対照的にチベットを主な舞台としてシャングリ・ラという理想郷を世に出したジェイムズ・ヒルトンの『失われた地平線』(1933)を再読しながら再確認してみたい。
『歳月』に描かれるパージター一家の長女エレナ・パージターは、母ローズ・パージターの看病や、弟妹の世話、そして父エイベル・パージターを看取り実家を売りに出すまでのあいだ私的領域に閉じ込められていた。
『歳月』最終章の「現代」では、今やエレナがギリシャ、イタリア、スペインと、世界を旅して周り、自由を謳歌しているエピソードが引き出されていく。エレナは英国植民地の最重要地点であったインド旅行を終え、見た目はさながらジプシーのようである。そして彼女は、残された人生の中で見ておきたいものとして、「異なる文明」としてのチベットをあげる。
「ああ、インド。インドなんてこの頃じゃ何でもありはしない」エレナは言った。「旅行もずい分楽になったわ。切符を買うだけ、船に乗り込むだけでいいのだもの……でもね、死ぬ前に見ておきたいと思うのは」彼女は言いつづけた、「もっと別の何かなの……」[中略]「……別の種類の文明。たとえばチベットよ。何とかいう名の男の書いた本を読んでいたの――さあ、何という名前だったろう?」(417)
1937年に出版されたこの小説が最終章「現代」を1931-33年と設定しているのであれば、エレナが読んでいると思しきチベット関連の書籍について、ジェームズ・ヒルトンの『失われた地平線』を連想したくなる。『失われた地平線』は 1933年に出版され、その後出版された『チップス先生さようなら』が広く受け入れられると、『失われた地平線』も注目を浴びるようになる。1934年のホーソーンデン賞の受賞を経て、1937年にはフランク・キャプラによる映画化を通してさらに大衆に広まった、チベットを舞台とする認知度の高い作品である。エレナがヒルトンを読んでいるかどうかの検証は困難であるが、『歳月』の「現代」に設定されている時期は、大戦に向けたヨーロッパ―東アジア間の連動性が見られ、チベットを舞台に理想郷「シャングリ・ラ」の名を世界に広めた帝国ロマンス風作品が消費されていた頃である、ということは少なくとも確認できる。そうした時代背景を持つウルフの小説『歳月』において、インドを見てきたエレナの眼がチベットに向かうのは、文字通り、自分たちが生きてきたものとは何か異なる文明を見たいからなのだろうか。
本発表では、まずウルフの『歳月』に表象される西洋のチベット像を、ヒルトンの『失われた地平線』(1933)とともに再読する。崩壊していく世界の中にありながら捜し求められる新しい文明として 1930年代にチベットを描くこれらの作品を、第一次大戦前のグレート・ゲームから第二次大戦、そして冷戦を経た新冷戦下の今まで、という期間の中で、どのようにとらえていくことができるのか、考えてみたい。戦争や暴力が渦巻く西洋文明とは異なる文明として表されるチベット像を、列強がそれぞれの地政学的思惑を落とし込む緩衝地帯としてのチベットになぞらえてみると、そこにイギリスから中国(場合によっては太平洋も含んだ日本、アメリカ)までの一続きの動きが見えるかもしれない。
参考文献
Becker, Allienne R. The Lost Worlds Romance: From Dawn till Dusk. Greenwood, 1992.
Brantlinger, Patrick. Rule of Darkness British Literature and Imperialism, 1830–1914. Cornell UP, 1988.
Hilton, James. Lost Horizon. Vintage Classics, 2015.『失われた地平線』池央耿訳 河出文庫、2011年。
Masuzawa, Tomoko. “From Empire to Utopia: The Effacement of Colonial Markings in Lost Horizon.” positions: east asia cultures critique, vol. 7 no. 2, 1999, p. 541-572. Project MUSE, https://muse.jhu.edu/article/27932.
Mather, Jeffrey. “Captivating Readers: Middlebrow Aesthetics and James Hilton’s Lost Horizon.” CEA Critic, vol. 79 no. 2, 2017, p. 231-243. Project MUSE, https://dx.doi.org/10.1353/cea.2017.0018.
Woolf, Virginia. The Years. 1937. Edited by Hermione Lee, Oxford UP, 1992.『歳月』大澤實訳 文遊社、2013年。
石濱裕美子『世界を魅了するチベット―「少年キム」から「リチャード・ギア」まで』三和書籍、2010年。